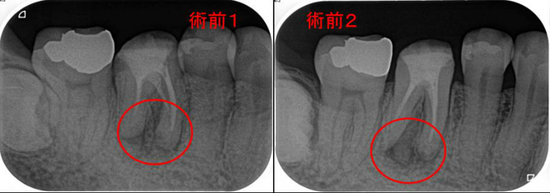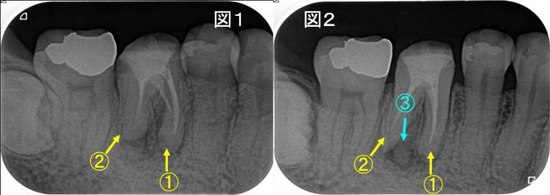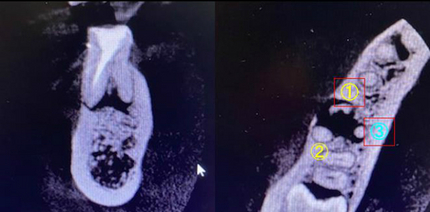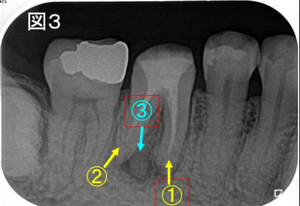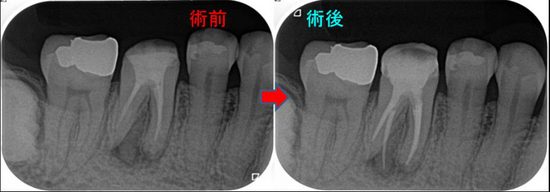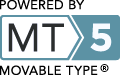歯内療法専門医の新旧診断法
- Posted by: eedental
- 2020年8月14日 09:09
- 歯内療法日記
患者さんは40代の女性
何度か治療しているが治らず2年以上前から膿が出るとのことで、
CBCTがある歯科医院へ転院そこでCBCTを撮り、
これは歯内療法専門医の歯科医院で治療した方がいいと説明され、
EEデンタルを紹介してもらい来院
奥歯の神経管は複雑でまず治療する前の【診断】が重要です。
CBCTがなかった時代は角度を変えてレントゲンを2枚撮り
術者の頭の中で歯の形を想像する。
すると
図1では根の数が2本に見えますが、
図2では②の陰に隠れた神経管③が確認できます。
また③の隠れた神経管は手づかずで治療している痕がなく、ここが腫れの原因と考えられます。
たぶん、この神経管を探して治療すれば治るだろうと推測していました。
が、
CBCTでは、
病変の位置大きさから、①、③が最近感染していることが分かり、
更に、神経管の太さや湾曲も分かる時代です。
ですから、
③同様に①も丁寧にやり直す必要があると分かります。
逆にいえば、②の根管は感染していないので、それなりのケアですみそう。
今回のようなケースは年に何本もあり、専門医であれば過去の経験から
「あ、このパターンね」と大体分かります。
ただ、このパターン 非常にリスキーで
・③の神経管が非常に分かりにくい場所から出てくる(壁やパフォ起こしそうな場所)
・③の神経管の軸がかなり外開きで①、②の神経管の軸とはかなり方向が異なる
・神経管の湾曲度がかなり大きい場合もあり、NI-TIファイルを折りやすい
など経験に当て始めます。
レントゲンで分かっても、手を動かしてきとんと感染源を除去出来ないと治らないので、
ある程度の「技術」というもは診断後に必要にはなります。
*宝探しの地図がCBCTで宝を探し掘る当てるのは人の技量ということです。
1回目に神経管を探し出し、2回目に膿が出なくなったのを確認し、
根管充填+レジンコア+仮歯まで
この後、半年程度仮歯で過ごしてもらいレントゲンで経過を見ていきます。
「治療前にまず診断を」というのを心掛けています(・∀・)ノ
- About
-
EE DENTALの
オフィシャルブログです!
- カレンダー
-
« 2020 8 » S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Archives
-
- カテゴリ
- 最近のブログ記事
- Recent Photos
- Tag Cloud
-
- オールセラミック ジルコニア 仮歯
- サーフボード
- ブログ
- レジン
- 歯内療法専門医 根管治療 マイクロスコープ
- 歯内療法専門医 根管治療 マイクロスコープ レジン
- 歯内療法専門医 根管治療 マイクロスコープ レジン治療
- 歯内療法専門医 根管治療 マイクロスコープ 虫歯
- 歯内療法専門医 根管治療 感染根管 マイクロスコープ
- 歯内療法専門医 根管治療 感染根管 マイクロスコープ レジン
- 歯内療法専門医 根管治療 感染根管 顕微鏡歯科 マイクロスコープ
- 歯内療法専門医 根管治療 顕微鏡歯科 マイクロスコープ レジン
- 歯内療法専門医 根管治療 顕微鏡歯科 マイクロスコープ レジン治療
- 歯内療法専門医 根管治療 顕微鏡歯科 レジン
- 歯内療法専門医 根管治療 顕微鏡治療 マイクロスコープ レジン
- 歯内療法専門医 根管治療専門医 マイクロスコープ レジン
- 3M ジルコニアクラウン セラミック
- AAE
- AAE アメリカ歯内療法学会
- AAE 根管治療 内部吸収
- 検索
- Links
- 購読
- Powerd By